

―――セイレーン
それは、美しい歌声で人々を惑わし喰らう魔性。
巨大な翼に鳥類の足。
鳥を象ったその姿は、しかしいつしか鱗を纏い海中を泳ぐ人魚へとその形を変えた。
セイレーンが姿を変えた理由。その背景には一つの“うた”があった。
これは、セイレーンが空から海にその棲みかを移したお話。
生きとし生けるすべての“いのち”へと繋がる、はじまりの伝承。
―――ひとりの少女とセイレーンの物語。
『暁の光射す白銀の衣纏いて 湛えるその眼差しは春の風のよう
優しき調べ紡がれ まどらかな声音満ち渡る すべてを慈しむ母なる子守唄よ
黄昏の光降る金色のヴェール被りて 微笑むその面差しは秋の月のよう
哀しみ癒すぬくもり やわらかな御手包み込む すべてを愛しむ母なる子守唄
―――la fortuna
願わくばお聴き下さい 我らは貴女様の最愛の子ども その慈しみを豊かな実りを与え給へ
―――la fortuna
願わくば聴き届け下さい 我らは貴女様の最愛の子ども あの哀しみを大いなる罪を許し給へ』
純白の衣を纏い、愛しそうに赤子を抱く女神の像。
色とりどりのステンドガラスを透けて、七色の光が講堂を満たす。高い窓に描かれているのは、楽園に遊ぶ天使や人、動物をモチーフとした絵画だった。唱われる讃美歌に色彩を与え、まるでここが楽園であるかのような幻をみせていた。
「―――はい!駄目よ駄目!」
しかしその一声に、美しいコーラスは震える。途端、僅かな反響だけを残して掻き消えてしまった。差し込んでいた光も心なしか影り、楽園の幻まで霧散する。
声の主はチェーンのついた眼鏡をかけ、癖のあるブロンドの髪を後ろで一つに束ねた妙齢の女性。はっきりとした目元をすがめ、大きく溜め息をつく。
ピアノを奏でていた彼女は徐に立ち上がると、壇上に三列に並んだ少年少女の元へ歩き出し、前列端にいた一人の少女の前で止まった。
「フィーさん! 貴女は力みすぎていて、全然声が溶けていません! 貴方の歌ばかり悪目立ちしているのです。それが上手いのならまだ良いでしょう。ですが悲しいことに、テンポも音も外していては、どうしようもありませんよ!」
「・・・っ・・」
叱られた少女、フィーはその細く小さな体を嵐に晒された小鳥のように震わせた。アーモンドの形をした濃青色の瞳は瞑られ、桜貝のような唇はつぐまれる。
「ごめん、なさい・・マルシア先生・・・」
胸の辺りで結わいた二つのおさげに顔を埋めながら、絞り出すように謝るしか出来なかった。ただでさえ華奢な少女は、まるでこの場から消えてしまいそうに小さくなる。
その脅え様を見たマルシアは、嘆息と共に首を振った。
「貴女は歌も態度も、もっとテオドールさんを見習った方がいいですね」
マルシアはそう言うと、舞台の中央に一人立ちソロを務める少年に手を伸ばす。
「・・・・・」
呼ばれた少年、テオドールはそこでようやく振り返ると、舞台の後ろを平睨した。
顎の辺りで切り揃えられた髪は内側に弛くカールを巻き、色素の薄い髪がその重たさをなくしている。容姿は硝子細工で出来た彫像のように整い、夜の森を映したような新緑の瞳がその神秘性を高めていた。
皆の視線を一斉に集めても、全く動じることのなく無表情のままだ。その碧水を湛えた瞳と目が合ってしまい、フィーは気まずくなって視線をずらす。
自分の不甲斐なさと練習を止めてしまう申し訳なさで、涙まで込み上げてくる始末だ。しかしここで泣いては更に足を引っ張ってしまうと、長いスカートを握りしめ懸命に堪える。
―――叱りを受けるのはもう数えきれなかった。
ここは聖フォルトゥナ教会。
第七星の日に開かれる、楽しんで歌うだけの聖歌隊ならこんなことにはならない。ピアノやオルガンの奏者も教会のシスターであれば、どんな歌でも優しく許してくれるだろう。
だが、これは歴とした授業なのだ。
「いいですか。もう間もなく女神フォルトゥナに歌を捧げる、年に一度の祭典が開かれます!貴方達三十人はこのテーナ地方全域から選ばれた聖歌隊の歌い手なのですよ! 祭典ではメイン、そしてトリを飾る大任を負っているのです! その自覚をもっと高めなくてはなりません! 選ばれたくとも選ばれなかった者達の分まで、そして女神に歌を捧げることを許された栄光を胸に!他の皆も、フィーさんばかりと油断していてはなりませんよ!」
聖堂にこれでもかと反響した教師の叱咤に、生徒達の間には緊張が走った。語られた責務に神聖な空気が重厚を増し、より一層萎縮させる。
いつもは冷静なマルシアだったが、音楽のことになると人が変わったように熱くなる。更に言い募ろうとした彼女を遮ったのは、教会の屋根に取り付けられた銀色の鐘の音だった。
乾いた、しかし重量感のある響きが梁を振動させ身体にも木霊する。合間から聞こえた鳥の羽ばたきが次第に遠ざかっていった。
「もうこんな時間ですか。・・・では、今日の練習はここまでにしましょう。号令を」
両手をおおげさに広げていたマルシアは、何事もなかったかのように歩き始め、舞台中央に立った。
入れ替わるように列に戻ってきたテオドールを待って、最後列の背の高い少年がお祈りの言葉を上げる。
「今日も女神フォルトゥナの御加護に感謝して、ありがとうございました」
「「ありがとうございました」」
両手を胸の辺りで組み、目を閉じる。皆で後に続き唱和した。
「夜の礼拝も忘れることなく!ではまた明日」
マルシアはそう言うと、ピアノの上に広げられた楽譜をしまいながらテキパキと帰り支度を整える。他の生徒達も、次々に壇を下りて蜘蛛の子を散らすように帰っていった。
テオドールももう用はないとばかりに、フィーになどは目もくれず去っていく。
最後にぽつりと残ったのは、フィーだった。
「・・・はぁ・・」
聖歌隊の為に貸しきられた広い聖堂に、一人取り残される。幾重にも讃美歌を響かせていたそこは、今は静寂に包まれた。
陽の光を反射して輝いていた窓画も、胸の内を映したように悲しげに見えてしまう。
フィーはしばし立ち尽くした後、女神像を振り返った。もう一度、女神にすがるような思いで一頻りお祈りを捧げた後、逃げるように教会を後にしたのだった。
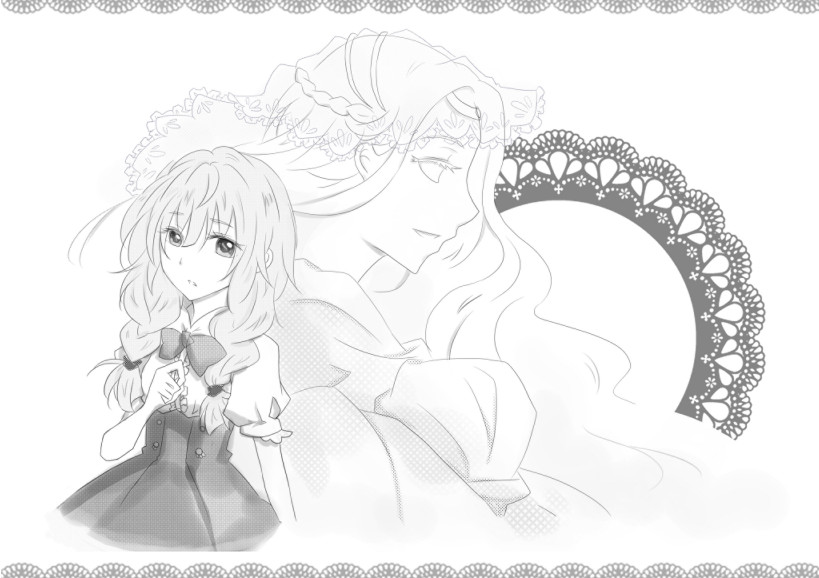

女神は仰った。
〈歌〉には奇跡を起こす力があると。
人々の歌は世界に溶け、凡ての事物を動かす力があると。
それは歌が女神から授けられたものであるから。
また、人が女神に愛されているからこその御業。
故に、女神の愛情を一心に受けている御子こそが、その歌の力を最大限に引き出せるという。
そういう古い伝承が、テーナ地方にはあった。

―――家への帰り道。
フィーの足取りは重かった。
帰れば母親から今日の出来事を尋ねられてしまう。本当のことを言うのも、ごまかすのもどちらも嫌でしようがなかった。
フィーが聖歌隊に選ばれたことを、フィー自身よりも喜んだのが母のリゼーヌだった。リゼーヌは熱心に女神フォルトゥナを崇め、毎週ある教会の説法を欠かさず聞きにいく程だ。
そんな母に、女神に捧げる歌の練習で度重なる失敗をしていることなど言える筈がなかった。
「・・・・・」
きちんと歌おうとすればする程、悪目立ちしてしまう。意識しすぎて逆にテンポがずれてしまう。
いっそ歌っているフリでもしようかと思ったが、フィー自身歌うことが好きだし、歌える場で歌わないなんてことはしたくなかった。教師であるマルシアに止められればフィーに抗う術はなかったが、何故かどれだけ叱咤をしてもマルシアは唱うなとは言わなかった。
それが優しさなのか厳しさなのかはわからなかったが、フィーが助けられているのは確かだ。
「はぁ・・・」
色々なことが頭を巡り、気持ちが沈んでしまう。このまま帰るとまた塞ぎ込んでしまう気がして、フィーの足は家とは反対の方向に向いた。
いつもは真っ直ぐに進む石畳を、右の方に曲がる。家々の隙間にある下り坂の脇道に身体を滑り込ませるように歩けば、小さな通りに出た。それは上の大通りの下に並走して伸びていた。風化した石造りの階段がまた更に下へと渡されている。
いよいよ潮の匂いが強くなる。古く急な螺旋階段を一足一足慎重に下りていく。両側には自分の背丈を越える壁。等間隔に空いた窓から、沈みゆく夕陽に照らされた海が覗く。
階段を下りきったそこは砂浜だ。 海水浴で使われるような場所とは違う。入り組んだ湾岸のせいで海流が急になっているからか、お陰で人気はなかった。
・・・ここなら誰もいない、よね。
そう思って空気を胸いっぱい吸い込む。そのまま歌いだそうとした矢先、上の大通りを走る馬車の音にビクついた。誰もいないと油断していたせいで必要以上に驚いてしまう。動悸する胸に手を当てつつ、フィーはより人気のない所を探して歩き出した。
少しずつ、ゴツゴツした岩が増え海にも岩礁が目立ってきた。砂浜というよりは岩場に変わってきた足元を慎重に選んで進む。
「こんなところあったんだ・・・」
ずり落ちそうになる肩かけ鞄を背負いなおす。スカートを手繰りあげて、両手をつきながら平たい岩場を登った。
ふと気がつくといつしか日が落ちていた。藍に塗り変わった空には、小さな星がきらきらと瞬き出している。心なしか肌寒くなってきて、フィーはケープの下で身を縮めた。
逃げるようにここまで歩いて来たものの、落ち着いてくると、どうしたかったのかよくわからなくなってしまった。何だか歌うことも億劫になってきて、その場で座り込む。
ただぼんやりと、さざ波の奏でる心地よい音色に耳を澄ませた。投げ出した足の下で、波が生き物のように寄せては返す。見渡す限りの夜の海と空は溶け合い、地平線も消えてまるで一つになったかのようだった。銀色の月明かりが反射して、たゆたう水面を蒼く染め上げる。
「・・・・・」
幻想的な風景に、身を委ねるように瞼を閉じる。胸にかかっていた靄が払われていき、ゆっくりと癒されていく心地がした。
そのままどのくらい経っただろうか。
ふと瞳を開いたその時、
「・・・・?」
―――歌声が、聞こえてきた。
芯の通った美しい歌声。
初めは風のさざめきとも思ったが、聞き間違えではない。海の音に寄り添うように紡がれる、フィーの知らない言葉。
一瞬で、心が捕らわれた。
気がつくと、フィーは声のする方へ向かっていた。
音を立てると泡のように消えてなくなってしまいそうで、静かにしかし素早く足場を渡る。
複雑に入り組み始めた入江に差し掛かる。街の裏手にあたる崖が右手に続いていた。その下に広がる岩礁の隙間から、身を屈めて覗き込んだそこには、
「・・・っ・!」
フィーは、息を呑んだ。
鼓動が、跳ねた。
浅瀬にいくつも突き出した岩が、塔のように聳える。
その一つにとまっていたのは、―――双翼の女性。
凜とした居ずまいに、人ならざる羽が映える。月光に照らされた紫紺の瞳が、宝石のようにきらきらと輝いていた。後ろに流れる長い髪はゆるく結わえられ、まるで天の光で織られたように滑らかだ。鳥類の足で岩の上に掴まり、遥か夜空を見上げ歌っている。
蒼穹の天と地を背に、浮かび上がる白い輪郭。
―――美しかった。
その姿も、歌も何もかも。
この世のものとは思えない、正に至宝のようだった。
聖堂のどんな絵画にも負けない、女神フォルトゥナ像さえも霞ませる姿。今まで聴いたどんな名手の歌も忘れさせる程の歌声。
「・・・・・」
ただ呆然と、見とれてしまった。
フィーはまるで自分が石になってしまったかのように息をするのも忘れて、ただ聞き入り見入っていた。
その場にどれ位いたかわからない。
カテドラルの鐘のような落ち着いた声音が響き渡り、最後に同じフレーズを何度か繰り返した後、歌は儚げに終わった。
後には余韻が馥郁のように残り、フィーはぼんやりとその場で惚けてしまった。魂を揺さぶる、何物にも形容し難い衝撃。
目の前で、彼女は腕代わりの翼を悠然と広げた。
そして二度大きく羽ばたくと一思いに跳躍し、天の川が輝く星の海へと、飛び去っていったのだった。
「あ・・・・!」
フィーは思わず虚空に腕を伸ばし、小さくなる影を追う。
掴める筈はなかった。
まるで全てが幻であったかのように、夜の海の風景だけが広がる。
しかし、フィーの耳元には確かにあの歌声が残っていた。
「・・・・・」
星降る夜。海の色に照らされた、刹那の邂逅。
しばらくの間、フィーはその場から動くことは出来ないでいた。

―――女神は仰った。
〈歌〉には奇跡を起こす力があると。
それは、存在そのものさえも変える力があると。
人と動物の狭間の生き物。彼らは歌の力でその姿を変質させていったという。
しかし、それは女神の歌ではなく魔性の歌に当たるとされた。
故に、女神から授けられし歌以外は、歌ってはならないという戒め。
教会の聖職者以外は、歌を作ってはいけないのだ。
